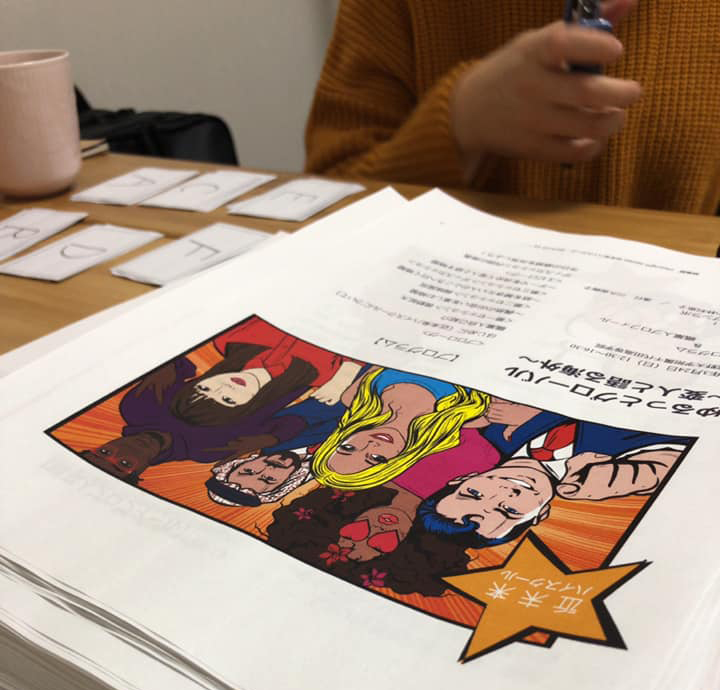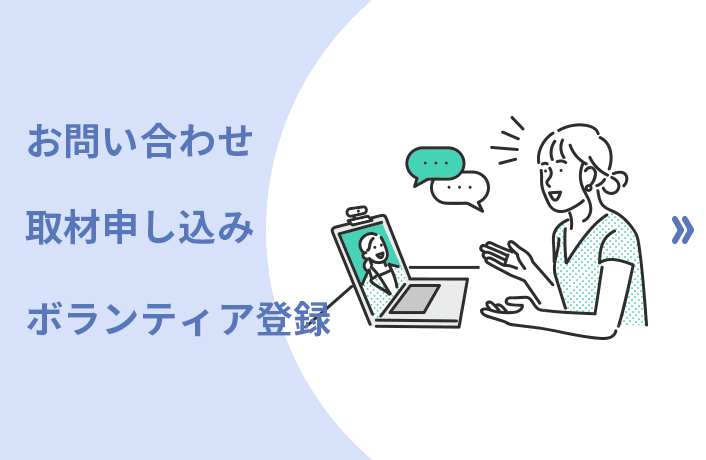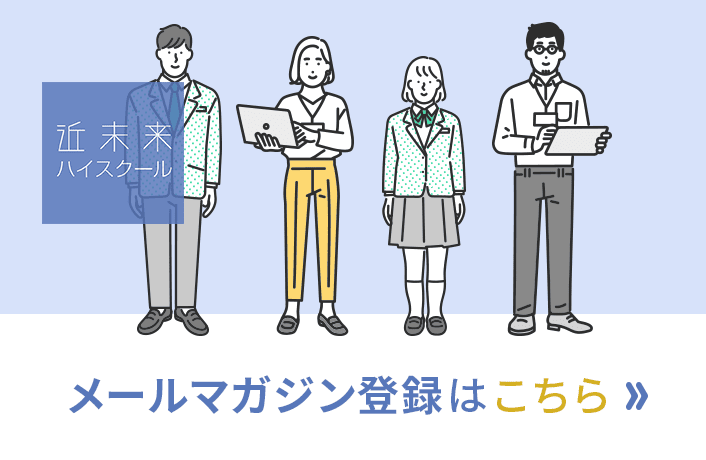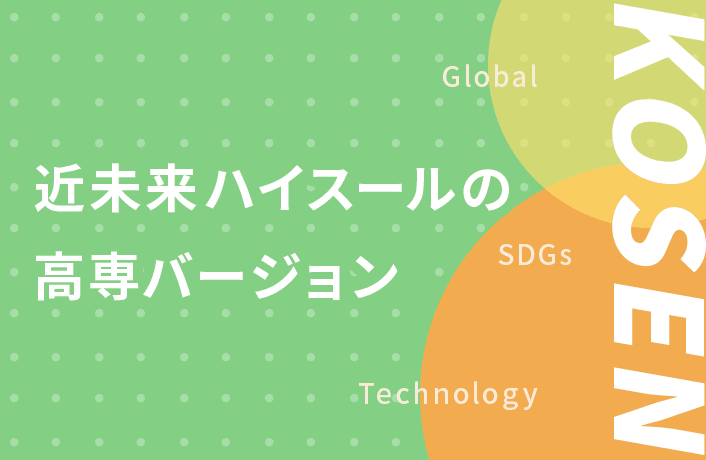哲学とサイエンスの畜産農家〜梶岡牧場:前編
コラム

近未来ハイスクールで変人の皆さんに熱く語っていただいた内容をアーカイブしていく本シリーズ。
今回ご登場いただいたのは、山口県美祢市を拠点に繁殖・肥育・提供と一気通貫の経営を行う梶岡牧場の梶岡秀吉さん。梶岡さんには、山口の徳山高専や東京の戸山高校で実施した近未来ハイスクールでも登壇いただいています。今回は三田国際学園 で生物を教える大野智久先生によるインタビューを前後編に分けてお届けします。

■殺処分対象の雄の乳牛を飼育
ーー梶岡牧場では、牛の繁殖・育成、出荷まで一貫して担っておられるとのことですが、まずはそのような形態で運営されている理由をお聞かせください。
「じつは私たちはもともと、りんごなどの果樹園を営んでいたんです。でも、果樹園は台風などの影響を受けるリスクが大きく、収益を安定化しづらいという課題がありました。そこでより安定化した経営のために1986年に畜産に参入した経緯があります。
一般的に、乳牛の雄の多くは価値のないものとして残念がられたり産まれてすぐお肉になったりもします。梶岡牧場は、その雄牛たちを立派に肥育し,価値のある命とする取り組みを行っていることが特徴です。
当初は、近隣の肉屋やレストランから依頼を受け、牛や餌を預かって飼育する牛の保育園のような形態で運営していました。しかし、そのスタイルでは牛の品種や飼い方などコントロールできない要素が多く、自分たちが理想とする飼育が出来ないこともありました。
でも、自分で牛を持ち、すべてを自分たちで担うようにすれば、市場に出す価格も自分たちで決められるようになります。そうすることで理想とする育て方も追及できると考え、繁殖から出荷まで一貫して行う現在のスタイルに行き着きました。
また、『肉になる運命が決まっている牛たちには、生きている間は快適に過ごしてほしい、肉になったあとは食べた人が笑顔になってほしい、そうやって命をつないでいきたい』という思いのもと、飼育環境やエサなどにもこだわっています。それがアニマルウェルフェアにもつながっているのかもしれません」
ーー一般的な畜産農家との違いを教えてください
「一つのマスに6〜10頭程度でのびのびと育てています。みなさんからは贅沢と言われますね。
雄牛が喧嘩をして角でお互いの体を突き合った場合、肉としての価値が一突きで10万円下がると言われています。それを避けるために角を切り落とすのが一般的ですが、うちではストレスになるので切り落としていません。
人間もストレスがかかると酸化体質になると言われていますが、牛も同じだと考えているためです。」
また、牛の寝床に敷く敷料は、一般的に使われている建築廃材ではなく、敷料用に木を削ったものを使用しています。ちなみにこの木は、有機農業の認証規格をクリアするクラスの品質のものを使っているんですよ」
■よい循環を生み出す堆肥作りの秘密
ーーその他にこだわっていることはありますか?
「糞尿の処理です。先日いらっしゃったレストランのオーナーが『どうしてこんなにきれいなんですか?』と驚かれていましたが、うちでは2週間に1回床替えをしています。人間でもトイレでは寝られませんよね。それと一緒です。
糞尿の処理にはコストがかかります。なかには糞尿をそのままきゅう肥として農家へに卸しているケースもありますが、そのままの状態だと分解に窒素を必要とするため、逆に田畑がやせてしまいます。それを気にした農家から搬入を断られてしまうと処理先がなくなり、床替えすらできなくなってしまうのです。ひどいところでは1年も替えないところもあります。
そこで梶岡牧場では、手間をかけて糞尿を商品価値のある堆肥へと作り変えています」
ーー梶岡牧場で生産される堆肥は3か月待ちとのことですが、なぜそこまで支持されているのでしょうか?
「私たちの堆肥には、10の7乗から8乗くらいの微生物が含まれています。堆肥としては高級品かもしれませんが、『微生物素材としてはすごく安い』とみなさんに喜んでいただいていますよ。
一流レストランに卸している農家さんにも愛用いただいていますし、最も遠方では北海道のアスパラ農家さんにも卸しています。輸送コストを考えると割高ですよね。北海道に多くの畜産農家があるにも関わらず、同じレベルの堆肥が北海道にないということで指名でご用命いただいています」
ーーそれだけの高品質を実現できる理由はどこにあるのでしょうか?
「一番は発酵技術です。お酒造りと同じような手法で水分や温度、材料など細かくコントロールしています。
一般的なの畜産農家は、牛を育てることだけにフォーカスしているので、堆肥作りまで手が回らないのかもしれません。設備投資も必要ですから、高いハードルといえます。堆肥で利益を出そうとすれば最初から商品として設計しないと難しいのですが、私たちはそれを実現しています」
ーー熟練した技術も必要なのでは?
「水分や温度のデータを活用すると同時に、オンラインで写真などをスタッフと共有し、タイミングや感覚的な判断を養えるようにしています。経験を積んでいけば、そういったデータに加えて臭いなど人間の感覚でも判断できるようになりますよ」
ーーかなり手の込んだことをされていますが、利益はあるのでしょうか?
「廃棄物ではなく商品として堆肥作りをデザインしているので、事業としてしっかり利益を出せています。物質の循環も大切ですが、私たちはお金の循環も重視しています。梶岡牧場の堆肥を使用した結果、おいしい野菜が生産され、農家にとっての利益になる。そんなよい循環をめざしています」
梶岡牧場 Webサイト
梶岡牧場 オンラインショップ
梶岡さんのブログ
前編 | 後編

 Prev
Prev